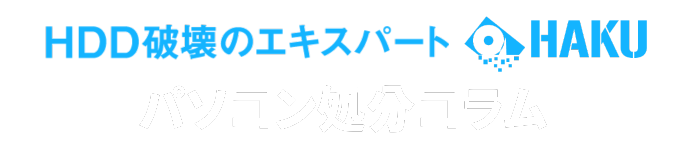老朽化したオンプレミスサーバーや使わなくなったラックマウント型サーバー、あなたの会社ではどう処分していますか?
「とりあえず初期化すれば大丈夫」
「業者に出せば消してくれるはず」
そんな“なんとなく”の処分方法は、重大な情報漏洩のリスクを招く可能性があります。
実際、企業や自治体では、サーバー内の情報が外部に流出したことによる信用失墜・損害賠償・行政処分といった深刻な問題が年々増加しています。
この記事では、
- サーバー処分がPC以上に慎重であるべき理由
- データ消去の正しい手順と、証明書の活用方法
- 業者選びで絶対に外せないチェックポイント
- 自治体や法人の実際の処分事例
- リサイクル・無料回収など複数の選択肢
まで、安全かつ確実にサーバーを処分するための知識を網羅的に解説します。
情報管理責任を担う情シス担当者や総務担当者の方は、ぜひご活用ください。
サーバー処分が難しい理由とは?
データの重要度が桁違いに高い
サーバーは単なるデバイスではなく、企業や組織の中枢を支える情報基盤です。
その内部には以下のような機密性の高いデータが保存されている可能性があります:
- 顧客データベース(個人情報・住所・電話番号など)
- 会計データ・取引履歴・売上分析情報
- 業務システムのバックアップファイル
- メールサーバーの送受信ログや添付ファイル
- 教育機関や自治体なら、児童・住民情報・申請履歴
万が一、適切に消去されていないデータが復元された場合、重大なコンプライアンス違反・損害賠償につながる可能性があります。
データ消去だけではなく「証明」が求められる時代
特に法人や自治体では、以下のような監査・審査を受けることが一般的です:
- ISMS(ISO27001)やPマーク更新時のセキュリティ監査
- 取引先企業による外部監査
- 内部統制(J-SOXなど)の整備チェック
これらの場面では、「サーバーをどう処分したか」だけでなく、
- どのようにデータを消去したのか?
- 誰がいつ処理したのか?
- その証拠としてのデータ削除証明書があるか?
といった第三者に対して“説明可能な証拠”があるかどうかが問われます。
HDDのRAID構成やサーバー筐体の特殊性も影響する
また、サーバーはPCとは違い、以下のようなハードウェア的な複雑さも存在します:
- RAID構成(複数台のHDDで構成)になっている
- ホットスワップ対応のHDDが取り外されていない
- 筐体サイズが大きく、一般的なごみとして出せない
- 電源や管理ソフトウェアと一体化している(UPS・NAS・仮想化環境など)
このため、「物理的にどう分解し、どこにどう依頼するか」まで事前に考えておく必要があるのです。
処分前に準備すべきチェックリスト
サーバーを安全・適切に処分するには、いきなり破棄するのではなく、事前にやるべき確認事項を丁寧に整理することが重要です。
ここでは、廃棄前に必ず確認しておくべき項目を法人・自治体・個人を問わず共通するチェックリストとしてご紹介します。
保存データの棚卸しを行う
まず最優先で行うべきは、サーバー内にどのようなデータが残っているかの把握です。
✅ チェックポイント:
- ユーザー情報(ID、パスワード、連絡先など)
- 顧客リスト・商談履歴・請求データ
- 社内システムのバックアップ(メール、会計、業務ログなど)
- 仮想サーバーや共有フォルダの存在
- 管理者アカウントやリモートアクセス設定の有無
これらのデータは、一部でも復元された場合、深刻な情報漏洩につながる恐れがあります。
内蔵ストレージの構成と取り外し可否を確認する
✅ 確認すべきハードウェア情報:
- ストレージ構成(HDD/SSDの台数、RAID構成の有無)
- ホットスワップ対応の有無
- ストレージがサーバー筐体内蔵か外部ストレージか
- ベンダー固有の管理ツール(Dell iDRAC、HPE iLOなど)の存在
これらの構成により、物理破壊すべき部品の特定や業者への依頼方法が大きく変わるため、事前の把握が重要です。
処分対象の資産情報を台帳に記録しておく
法人の場合、情報システムや総務部門では、IT資産管理台帳や廃棄証明記録への記載が必須です。
✅ 台帳に記録すべき内容:
- 機種名・シリアル番号・導入年月
- 処分予定日・廃棄理由
- 対応担当者・上長の承認記録
- 処分方法(業者委託、自社破棄など)
- データ消去証明書の有無
台帳化することで、社内監査・外部監査時の説明責任を果たせるようになります。
保守契約・リース契約が残っていないか確認する
意外と見落とされがちなのが、メーカーや保守会社との契約状況のチェックです。
- リース契約中であれば、勝手に処分すると違約金が発生する可能性あり
- 保守契約が残っていれば、廃棄と同時に解除・精算の手続きが必要
→ 契約情報が不明な場合は、調達部門やベンダーに事前確認を行いましょう。
廃棄に関する社内承認ルートを確認しておく
企業・自治体では、サーバー処分時に以下のような稟議や承認が必要なケースが多くあります。
- 管理部門・上長・IT統括部門の承認
- 処分委託業者の事前選定
- 廃棄に関する社内フロー(例:機器番号通知、台帳更新、証明書取得)
無断で処分を進めると社内手続き違反となり、後で責任を問われる場合もあるため注意が必要です。
✅ 処分前の準備チェックリストまとめ
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| データの棚卸し | 保存内容をすべて把握・確認する |
| ストレージ構成 | HDD/SSDの台数、RAIDの有無を確認 |
| 台帳管理 | シリアル・導入日・担当者記録を残す |
| 契約確認 | リース・保守契約の状況を確認 |
| 社内承認 | 稟議・ルール・承認ルートを明確にする |
データ消去の正しい方法
サーバーの処分で最も重要なのが、データを“完全に”消去することです。
初期化や削除だけではデータが残る可能性があり、情報漏洩のリスクを完全に排除するには、論理消去と物理破壊の正しい使い分けが必要です。
論理消去:ソフトウェアでの完全削除
✅ 特徴:
- データを完全に“読み出せない状態”に上書きまたは無効化
- HDDやSSDを再利用したい場合に有効
- 消去作業後に専用ログやレポートを出力できるソフトもある
🔧 主なソフトウェア(例):
| ソフト名 | 特徴 | ライセンス |
|---|---|---|
| Blancco Drive Eraser | 国際認証あり。消去証明書出力対応 | 有料(法人向け) |
| DBAN | 無料。基本的な上書き消去に対応(HDD向け) | 無料 |
| Cbl Data Shredder | 複数回上書きやDoD規格に対応 | 無料 |
| WipeDrive Enterprise | ISO/DoD対応。法人用リモート消去機能もあり | 有料 |
📌 特に法人用途では、ISO15408やNIST 800-88などの消去基準に準拠しているソフトを使うと監査対応も安心です。
⚠ 論理消去の注意点:
- RAID構成の場合、消去操作は物理ディスク単位で行う必要あり
- SSDではウェアレベリング機能の影響で、完全な上書きができないことがある
- フリーソフトはログ出力や証明書発行に非対応なものもある
→ よって、HDDは論理消去で対応可、SSDは併せて物理破壊推奨が基本方針になります。
物理破壊:読み取り不可能にする最終手段
✅ 特徴:
- ストレージ自体を破壊し、物理的に読み出し不能にする方法
- データ復旧不可能な状態にできる
- 安全性・信頼性の観点で、法人や自治体では最も選ばれる手段
🔨 主な物理破壊方法:
| 方法 | 内容 | 安全性 |
|---|---|---|
| 穿孔(クラッシャー) | 専用機やドリルでHDD/SSDに複数の穴を開ける | ◎ |
| 粉砕(シュレッダー) | 機械で媒体を細かく裁断・破砕 | ◎ |
| 磁気消去(デガウサー) | 強磁場でデータを無効化(HDDのみ有効) | ◯(HDD限定) |
| 焼却(非推奨) | 一般家庭では危険/毒性ガスリスクあり | × |
証明書が必要な理由と活用方法
証明書(データ消去証明書・物理破壊証明書)は、以下のようなシーンで“処分の正当性”を裏付ける重要書類となります:
- ISMS(ISO27001)やプライバシーマークの監査資料
- 情報漏洩事故時の社内説明・顧客対応
- 契約上の証明義務(SLA/データ処理契約)
- 自治体の文書保存要件
✅ 証明書に記載すべき内容:
- 対象機器の型番・シリアル番号・台数
- 処理方法(論理消去/物理破壊)
- 実施日・担当者・発行者名
- 写真やログファイル(可能なら添付)
✅ 結論:安全に処分するなら「論理消去+物理破壊」+「証明書」
| 処理方法 | 対象 | 効果 | 推奨 |
|---|---|---|---|
| 論理消去 | HDD・SSD | 再利用可/復元防止 | ◎(再利用前提) |
| 物理破壊 | 特にSSD | 読み出し不可能 | ◎(安全重視) |
| 証明書 | 法人・自治体 | 処分の証拠 | ◎(監査・責任対応) |
処分業者の選び方とチェックポイント
サーバー処分を安全に行うには、信頼できる業者の選定が欠かせません。
しかし、「無料回収」「データ消去対応」といった言葉だけを鵜呑みにして依頼すると、情報漏洩やトラブルに発展するリスクもあります。
このセクションでは、優良な処分業者を選ぶための判断基準と、避けるべき業者の特徴を解説します。
優良業者を見分けるポイント
✅ 1. セキュリティ認証の取得
- **ISO27001(ISMS)やRITEA(情報機器リユース・リサイクル協会)**などの第三者認証を取得しているか?
- マイナンバーガイドライン準拠など、自治体対応経験の有無
→ 認証があることで、データ取扱体制の信頼性が担保される。
✅ 2. データ消去・破壊の対応方式が明確
- 論理消去 or 物理破壊のどちらに対応しているか?
- 使用ソフトや破壊方式、RAID構成対応の有無まで記載があるか?
- 消去・破壊の前後でログ取得や証明書の発行ができるか?
→ 「処理済み」と口頭で言うだけでは不十分です。
✅ 3. 証明書の発行形式と信頼性
- データ削除証明書・物理破壊証明書をPDFまたは紙で正式発行してくれるか?
- 機器ごとのシリアル記録、処理日、実施者の記載があるか?
📌 監査対応や社内報告が必要な場合、証明書がない業者は避けましょう。
✅ 4. 引取・回収対応の柔軟性
- オンサイトでの引取/訪問回収の対応があるか?
- ラック型・重量機器への対応力(人員・機材)の有無
- 地域ごとの対応エリアを事前に確認
→ 特にサーバールームがある法人では、物理的な運び出し対応力も重要です。
✅ 5. 情報管理ポリシーの公開
- 個人情報・機密情報の取り扱い方針が明記されているか
- 廃棄品の二次流通や部品流用ポリシーがあるか
→ 再利用品が勝手に売られていた、という事例は現実に存在します。
避けるべき業者の特徴(要注意)
- 「無料回収」とうたいつつ、消去方法や処理報告が一切不明
- 回収後に音信不通、証明書を発行しない・遅い
- シリアル番号の記録がない(誰のサーバーかわからない)
- 担当者名や会社所在地の記載が曖昧
- 極端に安すぎる価格(裏で部品転売の可能性も)
✅ 見積もり時に聞くべき質問まとめ
| 質問内容 | 理由 |
|---|---|
| データ消去はどの方式ですか? | ソフト/物理破壊どちらか確認 |
| 証明書は発行されますか? | 監査・社内報告に必須 |
| 機器台数が多い場合の対応は? | 回収・搬出体制の有無を確認 |
| シリアル管理はできますか? | 万が一のトラブル追跡のため |
実際のサーバー処分事例(法人・自治体など)
実際にサーバーを処分した現場では、手順や意識の違いによって、成功例と失敗例が大きく分かれています。
ここでは、企業・自治体・教育機関などのリアルな処分事例を通して、現場で何が起きたのか、どんな対策が有効だったのかを紹介します。
事例①|某自治体:ログ管理と証明書で万全のセキュリティ対策(成功例)
背景
ある地方自治体では、住民票や納税関連のシステムに使われていたオンプレミスサーバーの更新に伴い、旧サーバーを廃棄する必要があった。
対応内容
- RITEA加盟の業者に物理破壊を依頼
- 各サーバーのシリアル番号と処理日時を記録
- 処分業者から写真付き証明書+処理ログを受領
- 内部監査用に台帳保管+外部監査時にも提示できるようにした
成果
- 情報公開請求にも対応可能な資料を残せた
- 管理部門と情報システム部門が連携し、一貫した管理フローを構築
事例②|中堅製造業:初期化だけで返却しトラブル発生(失敗例)
背景
社員PCと併せてリース契約していたサーバーを契約満了で返却。
担当者は「初期化しておけば問題ない」と判断し、特別な消去処理をせずに返却。
問題発生
- リース会社側で復元ソフトを使ったチェックを実施
- 顧客情報や人事ファイルが未削除で残っていた
- 重大な情報漏洩リスクとみなされ、契約違反として報告書を提出する事態に
教訓
- 「初期化=安全」は誤解だった
- 現在は「物理破壊+証明書取得」を処分のルールに変更
事例③|私立大学:学生データ保護のため安全処分(成功例)
背景
毎年数百台の学内用PCおよびラックマウント型サーバーを更新している某私立大学。
サーバーには学生のレポート・出席管理データ・学内申請ログなどが格納されていた。
対応内容
- 外部の専門業者にサーバー単位での物理破壊を依頼
- 消去証明書を保護者説明資料に添付
- 処分費用は年間予算に組み込み、定期的なリプレース体制を整備
成果
- 学内からのトラブルゼロ
- 保護者や監査部門からの信頼向上
✅ 処分事例から学ぶポイント
| 教訓 | 意味すること |
|---|---|
| 証明書があると安心 | 説明責任やトラブル防止に有効 |
| 初期化だけでは危険 | 特に法人ではデータ復元リスク大 |
| 組織的にフロー化すべき | 個人判断ではなく社内ルールが必要 |
サーバー処分の選択肢(リサイクル・売却・無料回収)
サーバーの処分にはさまざまな手段があり、処分対象の状態・使用年数・設置場所・セキュリティ要件などによって適した方法が異なります。
このセクションでは、代表的な3つの処分方法について、特徴・メリット・デメリットを比較してご紹介します。
① リサイクル(PCリサイクル法対応 or 自治体連携)
✅ 特徴
- PCリサイクルマークのある機器であれば、メーカーが無料回収
- または自治体の「小型家電回収」制度で資源として処理可能(法人は対象外が多い)
メリット
- 無償で処分できる可能性がある(家庭用のみ)
- エコ・環境負荷削減に貢献
デメリット
- 法人利用のラック型サーバーや業務用機器は対象外が多い
- データ消去は利用者自身の責任(証明なし)
向いているケース
- 家庭用・個人使用の小型サーバー
- すでに初期化済み・重要データが含まれない場合
② 売却(リユース・中古業者への買取)
✅ 特徴
- 使用年数が短く、状態の良いサーバーは中古再販ルートで買い取ってもらえる可能性あり
- 再販目的の業者では、メンテナンスやリファービッシュ後に市場へ再流通
メリット
- 処分どころか収益化できる可能性あり
- 一部業者では消去対応や証明書発行も含まれる
デメリット
- データ消去レベルや処理の透明性が低い業者もある
- 中古業者のなかには、安価に仕入れて再販のみ行う業者もあり注意
向いているケース
- 3年未満で使用・外観や動作に大きな劣化なし
- 法人で再利用計画がなく、証明書付き対応を希望
③ 無料回収サービスを利用する
✅ 特徴
- 「無料回収」をうたう処分業者に依頼し、送料のみ or 出張回収無料で引き取ってもらえるケース
- HDDやSSDの物理破壊、証明書発行もオプションで対応してくれるところもある
メリット
- コストを抑えながら安全性も確保できる(条件による)
- 台数が多い場合も一括で処分可能
デメリット
- 一部業者は「無料」で引き取りつつ、消去作業はオプション(または未対応)
- 回収後の流通先や処理方法が利用者に開示されないこともある
向いているケース
- セキュリティ対策を施しつつ、費用も重視したい法人
- 台数が多く、回収や証明書発行も必要な自治体・団体
✅ 処分方法別の比較表
| 方法 | 安全性 | コスト | 証明書発行 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| リサイクル | △(消去自己責任) | ◎ | ✕ | 家庭用・簡易機器 |
| 売却 | ◯(業者次第) | ◎(収益化可) | ◯(要確認) | 稼働年数が短い法人 |
| 無料回収 | ◎(証明可) | ◎〜◯ | ◎(対応業者) | 法人・自治体 |
📌 処分方法を選ぶ際のポイント
- 「とにかく無料」ではなく、「無料で安全な業者」かどうかを確認
- 業者サイトで「データ消去方式」「証明書サンプル」「会社概要(法人番号等)」の記載があるか?
- 自社のセキュリティポリシーに準拠した方法を選択することが肝心です。
まとめ・安全な処分のための行動チェック
サーバーの処分は、単なる廃棄作業ではなく、**企業や組織の信頼と情報セキュリティを守るための“重要なプロセス”**です。
不適切な処分は、情報漏洩・損害賠償・監査不備といった深刻なリスクを招きかねません。
この記事を通じて、安全で確実なサーバー処分には「事前準備・データ消去・業者選定・証明書の取得」が不可欠であることをご理解いただけたと思います。
✅ 処分時に守るべき重要ポイント
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| データ棚卸し | 機密情報や顧客情報が残っていないか確認 |
| ストレージの特性把握 | RAID構成やSSDが含まれているか? |
| 台帳・契約の整理 | 保守契約・リース・社内稟議の確認 |
| 消去手段の選定 | 論理消去 or 物理破壊+証明書発行 |
| 信頼できる業者選び | 認証・対応実績・証明内容を確認 |
✅ 今すぐできる“安全なサーバー処分”の3ステップ
- 社内の不要サーバーの棚卸しを行う
→ 保存データ・使用状況・契約情報を確認 - 処分方針を明確にし、信頼できる業者を選定
→ 証明書の有無・処理方式を比較して判断 - 処分結果を文書化・社内台帳に記録
→ 後の監査やトラブルに備えて、証明書や写真を保管
💡 迷ったらプロに相談を!
「どの方法が自社に合っているかわからない」
「安全とコストを両立させたい」
そんな方には、サーバー廃棄や情報機器処分に対応した専門業者へ相談するのが一番確実です。
多くの企業・自治体で導入されている「物理破壊+証明書発行」サービスであれば、安心して任せることができます。
📢 サーバー処分は株式会社HAKUにご相談ください!
データ削除・パソコン処分のご相談は株式会社HAKUへ
HDD・SSDの安全な破棄、データ消去証明書の発行、法人向けの無料回収など、情報機器の処分に関するお悩みはお任せください。累計10,000社を超える取引実績を持つ処分のプロが解決します。