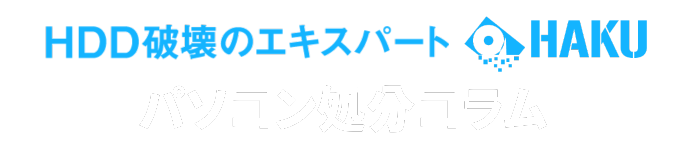パソコンを処分する前に忘れてはいけないのが「ハードディスクの取り外し」です。ハードディスク(HDD)やSSDには、写真や書類、ログイン情報など、あなたの大切な個人データがぎっしり詰まっています。そのまま処分してしまうと、第三者にデータを復元されてしまうリスクも。
「自分で取り外せるの?」「専門的な知識がないと無理なのでは?」と思われるかもしれませんが、実は、基本的な手順を守れば初心者でも対応できるケースが多いです。
本記事では、パソコンのハードディスクを自分で安全に取り外す方法を、デスクトップとノートPCそれぞれに分けて詳しく解説します。また、取り外した後のハードディスクの安全な処分方法や、パソコン本体の正しい捨て方についても紹介します。この記事を読めば、初めてでも安心してパソコン処分ができるようになります。
パソコンを処分する前に知っておきたい「データ漏洩リスク」
パソコンをそのまま捨てるのは危険
古くなったパソコンを「もう使わないし、捨てちゃおう」と気軽に処分してしまう方も少なくありません。しかし、パソコンの中には、思っている以上に多くの個人情報や機密データが残っています。メールのやり取り、家族の写真、ネットバンキングの履歴、仕事の書類など、削除したつもりでも実はデータとして残っていることも。
実際、過去には不要になったパソコンから個人情報が流出し、トラブルにつながった例が数多くあります。たとえば、ある自治体では、廃棄したパソコンから住民の個人情報が漏洩し、問題となりました。また、中古市場に出回ったパソコンを調査したところ、前の持ち主の履歴やファイルが復元できたという事例も報告されています。
こうしたリスクを防ぐには、パソコンを処分する前に「中のデータを完全に消去する」ことが不可欠です。
なぜハードディスクの取り外しが有効なのか?
データの大半は「ハードディスク(HDD)」や「SSD」といった記録媒体に保存されています。よく「初期化すれば大丈夫」と考える人がいますが、初期化やファイル削除では実はデータは完全に消えていません。専用のソフトを使えば、かなりの確率でデータを復元することが可能です。
このため、もっとも確実な方法は「ハードディスクを物理的に取り外してしまう」こと。取り外して保管しておけば、誰かに勝手にデータを読まれるリスクはなくなりますし、不要であればそのまま破壊するという選択もできます。
特に、会社で使用していた業務用パソコンや、ネットバンキングなどの重要な情報を扱っていたパソコンの場合は、なおさら注意が必要です。情報漏洩は信用問題にもつながるため、「処分の前にHDDを外す」という意識は、今やパソコンユーザーにとって常識ともいえる時代になっています。
自分でできる!パソコンのハードディスク取り外し方
取り外しの前に準備すべきもの
ハードディスクを取り外す作業は、落ち着いた環境で行うことでスムーズに進みます。まずは以下のような道具と準備を整えておきましょう。
用意するもの:
- プラスドライバー(精密ドライバーセットがあると便利)
- 静電気防止手袋またはリストバンド(可能であれば)
- 小物用のトレイや箱(ネジなどの紛失防止)
- 古いタオルや柔らかいマット(パソコンを置くため)
作業場所は、できれば床ではなく、静電気が発生しにくい木製の机の上が理想です。カーペットや布製のソファの上は静電気の発生リスクが高く、機器にダメージを与える可能性があるため避けましょう。
パソコンは必ず電源を落とし、コンセントを抜いた状態で作業してください。バッテリーが取り外せるタイプのノートパソコンなら、バッテリーも外しておきましょう。
デスクトップパソコンのハードディスク取り外し方
デスクトップパソコンの場合、構造が比較的シンプルで作業もしやすい傾向にあります。以下の手順で進めてください。
手順1:ケースを開ける
側面のパネルを外します。ほとんどのPCケースは背面のネジを数本外すことで開けられます。ケースによってはスライド式で開くものもあります。
手順2:ハードディスクの場所を確認
HDDはケース内の前方、もしくは下部に固定されていることが多いです。金属のラックのような場所にネジで取り付けられているのが一般的です。
手順3:ケーブルを外す
HDDには2本のケーブルがつながっています。1本はマザーボードにつながるデータ用(SATAケーブル)、もう1本は電源供給用(電源ケーブル)です。無理に引っ張らず、コネクタ部分を持ってゆっくりと外しましょう。
手順4:ハードディスクを取り外す
ネジで固定されている場合は、ドライバーでネジを外します。中にはレール式でスライドさせて抜けるタイプもあります。HDDが外れたら、別の布やクッションの上にそっと置いて保管しましょう。
ノートパソコンのハードディスク取り外し方
ノートパソコンは機種によって構造が異なるため、やや注意が必要です。以下のようなタイプに分かれています。
タイプ1:裏蓋に専用のHDDカバーがあるタイプ
もっとも簡単に取り外しができるタイプです。底面にある小さなフタ(HDDと表記されていることも)をドライバーで開けると、ハードディスクにすぐアクセスできます。コネクタを外して本体から引き出せばOKです。
タイプ2:底面カバーをすべて外すタイプ
裏蓋が一体型になっている場合は、底面全体のネジを外してカバーを取ります。このタイプでは内部のほとんどが見えるようになっており、HDDも固定ネジを外すだけで取り出せます。
タイプ3:キーボードの下にHDDがあるタイプ(古めの機種)
やや上級者向けの構造です。キーボードを取り外す必要があるため、事前にYouTubeやメーカーサイトで「型番+HDD 交換」などと検索し、分解方法を確認してから作業に入るのがおすすめです。
作業時の注意点
1. 静電気には要注意
静電気は電子部品の大敵です。冬場や乾燥している時期は特にリスクが高まります。作業前に金属製の棚やドアノブなどを触って静電気を放電してから作業しましょう。
2. ケーブル類の取り扱いは丁寧に
コネクタを無理に引っ張ると、マザーボード側の端子を傷つけてしまうことがあります。抜くときは必ず根元を持ち、左右に少し動かすようにしてから引き抜くと安全です。
3. 作業が不安なら無理をしない
「どうしてもネジが外れない」「構造が複雑すぎる」と感じたら、無理に続けるのはNGです。部品を破損してしまうと、処分業者やリサイクルショップで引き取ってもらえなくなるケースもあります。そういう時は無理せず、専門業者に相談しましょう。
取り外したハードディスクの処分方法
パソコン本体から無事にハードディスクを取り外した後、そのハードディスクをどうするかも重要なポイントです。ここでは、「保管する」「再利用する」「破壊・処分する」という3つの選択肢に分けて解説します。
そのまま保管する場合の注意点
ハードディスクに残っているデータを将来的に使うかもしれない…という場合、まずは安全な場所に保管しておきましょう。ただし、精密機器なので保管方法にも注意が必要です。
保管時のポイント:
- 静電気防止の袋(もしくはプチプチ)に包んでおく
- 高温多湿を避けた、涼しくて安定した場所に置く
- 外部からの衝撃を防ぐため、クッション材で保護する
また、もし定期的に確認する必要があれば、外付けHDDケースに入れてUSB接続すれば、通常の外付けハードディスクとして使用可能です。ケースはAmazonなどで1,000円前後から購入できます。
データを完全に消去して再利用する方法
取り外したHDDを外付けストレージとして再利用したり、別のPCに組み込む前に、データを**完全に消去する(ゼロ書き)**のがおすすめです。通常の「削除」や「フォーマット」では、データの痕跡が残ってしまいます。
安全にデータを消す方法:
- 無料ソフト「DiskRefresher」や「DBAN(Darik’s Boot and Nuke)」を使ってデータを上書き
- Windowsの「diskpart」コマンドでディスクのクリアを実行(上級者向け)
こうした消去方法を実行することで、個人情報の漏洩リスクを大きく減らすことができます。
自分で物理的に破壊する方法
「もう使わないし、保管の必要もない」という場合は、物理的に破壊するのが最も安全な方法です。実際にHDD破壊業者が行っている方法を参考に、自宅でもある程度の破壊は可能です。
個人でできる破壊方法(自己責任で実施):
- HDDのネジを外して中身(プラッタ)を取り出す
- プラッタにドリルや金属ピンで穴を開ける
- ハンマーで叩いて歪ませる・割る
内部の円盤(プラッタ)はアルミやガラス製で非常に硬いですが、物理的に傷をつけてしまえばデータを読み取ることは困難になります。
注意点:
- ガラス製プラッタは破片が飛び散る危険性があるため、ゴーグルと手袋を着用しましょう
- 作業は屋外や広いスペースで、周囲に注意しながら行ってください
専門業者に依頼する場合
「自分で破壊するのは不安」「安全確実に処分したい」という方は、HDDの破壊処分を専門とする業者に依頼するのもおすすめです。
たとえば、株式会社HAKUの「HDD破壊サービス」では、1台からでも受付可能で、物理破壊と証明書の発行も行っています。料金は1台あたり¥990〜対応しています。

【参考サイト】
株式会社HAKUのHDD破壊サービス:
https://datahakai.jp/lp02/
また、パソコンを無料で回収し、HDDのみを取り外して処理してくれる業者もあります。後述の「パソコン本体の処分方法」とあわせて検討してみてください。
パソコン本体の正しい処分方法
ハードディスクを取り外したあとのパソコン本体も、適切な方法で処分することが大切です。中には無料で回収してくれる業者もありますが、処分方法を間違えると不法投棄とみなされることも。ここでは、安全かつ合法的にパソコンを処分する方法を紹介します。
無料回収と有料回収の違い
パソコンは「資源有効利用促進法」により、自治体の粗大ごみでは基本的に処分できません。その代わり、以下のような方法で回収してもらうことができます。
1. パソコンメーカーの回収制度(PCリサイクルマーク)
2003年以降に販売された家庭用パソコンには、「PCリサイクルマーク」が付いている場合があります。このマークがあるパソコンは、メーカーが無償で回収・リサイクルしてくれます。各メーカーの公式サイトから申込みが可能です。
2. 環境省認定の回収業者を利用する(例:リネットジャパン)
リネットジャパンは国が認定している小型家電回収業者で、回収対象となるパソコンを無料で引き取ってくれます。申し込みはインターネットからでき、自宅まで回収に来てくれるのでとても便利です。
【参考URL】https://www.renet.jp/
3. 有料の自治体回収(例:一部自治体で指定引取場所へ持ち込み)
一部の自治体では、回収協力業者やリサイクル施設への持ち込みが可能です。ただし、回収には費用(3,000〜4,000円程度)がかかる場合があります。
4. 郵送での処分に対応している業社に依頼する(例:株式会社HAKU 送壊ゼロ)
株式会社HAKUの「送壊ゼロ」というサービスでは、送料のみの負担でパソコンの無料処分が可能です。さらに、データ削除も無料で実施してくれる、ハードディスクの取り外しやデータの削除が面倒な方にもおすすめです。 【参考URL】https://soukai0.com/
ハードディスクを抜いたパソコンを売却・譲渡しても良い?
HDDを取り外したパソコン本体を、「まだ使えるし、誰かにあげようかな」「ジャンクとして売れるかな」と考える方も多いはずです。実際、ハードディスクなしのパソコン本体も需要があります。
- 中古買取店やオークションサイトで販売
→「HDDなし」「動作未確認」などの記載をすれば、パーツ取りや自作ユーザー向けに売れることがあります。 - 知人に譲渡する場合の注意点
→個人情報が残っていないか、念のためHDD以外のデバイス(USBポートなど)もチェックしておきましょう。
また、「パソコンリサイクルマーク」がない古い機種でも、送壊ゼロやリネットジャパンやのような民間の処分サービスを使えば問題なく処分できます。
よくある質問とトラブルQ&A
ハードディスクの取り外しやパソコンの処分に関しては、初めての方だと不安や疑問も多いはずです。ここでは、実際によくある質問やトラブルをQ&A形式でまとめました。
Q1. HDDが見つからない、どこにあるかわからない…
A.
デスクトップパソコンでは、ケースの前方または下の方にあることが多く、金属のラックのような部分にネジで固定されています。ノートパソコンの場合は、底面のカバーを外すと見えることがほとんどですが、機種によっては内部深くに組み込まれていることも。
わからない場合は、パソコンの型番を検索して「〇〇型番 HDD 交換」などと調べてみましょう。メーカーサイトやYouTubeに分解手順が載っていることもあります。
Q2. 自分のパソコンはSSDだけど、取り外し方法は違うの?
A.
最近のパソコンはSSD(ソリッドステートドライブ)を搭載していることも多く、HDDとは形状や取り付け方法が異なります。
SATAタイプの2.5インチSSDであれば、HDDとほぼ同じ方法で取り外せます。一方、M.2タイプのSSDは、マザーボードに直接挿し込まれているスティック状のパーツで、小さなネジで固定されています。こちらも静電気に注意しながら、ネジを外して斜めに引き抜くことで取り外せます。
Q3. Macや一体型パソコンも自分でHDDを取り外せる?
A.
Macや一体型パソコン(ディスプレイと本体が一体になっているタイプ)は、Windowsパソコンに比べて分解が難しい構造になっていることが多いです。
特にApple製品は特殊なネジを使用していたり、分解に専用の工具が必要な場合もあります。慣れていない方が無理に開けようとすると、本体や液晶を破損する恐れがあるため、無理をせず専門業者に相談するのが安全です。
Q4. 取り外したHDDからデータを再利用したい。どうすればいい?
A.
取り外したHDDを再利用するには、「外付けHDDケース(SATA→USB変換)」を使うのが一般的です。Amazonや家電量販店で1,000~2,000円程度で販売されており、HDDをそのままUSB外付けストレージとして使えるようになります。
使わなくなったパソコンのHDDを、バックアップ用ストレージや録画用HDDとして活用する人も多いですよ。
Q5. ハードディスクを外したあと、パソコンはまだ使える?
A.
HDD(またはSSD)を取り外した状態では、パソコンは起動しません。OSがインストールされていないため、電源を入れても「起動デバイスがありません」といった表示が出るだけです。
ただし、HDDを別のストレージに交換したり、USBブートで使うといった応用は可能なので、再利用したい場合はパーツの追加や設定が必要になります。
まとめ
パソコンを処分する際に、もっとも注意しなければならないのがデータの漏洩です。たとえ電源が入らなくなった古いパソコンであっても、ハードディスクの中には個人情報や大切なファイルが残っている可能性があります。
そうしたリスクを回避するために、ハードディスクを物理的に取り外すという方法は非常に有効です。作業に必要な道具は少なく、デスクトップパソコンであれば比較的簡単に対応できます。ノートパソコンの場合も、多少の下調べをすれば初心者でも取り外せるケースが多くあります。
また、取り外したHDDはそのまま保管しても良いですし、データを完全に消去して外付けストレージとして再利用することも可能です。使わない場合は、物理破壊を行うか、専門業者に依頼して安全に処分することで、情報漏洩の心配をなくすことができます。
そして、HDDを取り外したあとのパソコン本体も、PCリサイクルマークのあるものはメーカーが無償で回収してくれますし、信頼できる回収業者に出すことで、無料または安価に処分が可能です。
パソコンの処分には手間がかかるように感じるかもしれませんが、「たった1つのハードディスクを外すだけ」で、あなたの大切な情報を守ることができるのです。
この記事を参考に、ぜひ安心・安全なパソコン処分を実践してみてください。
データ削除・パソコン処分のご相談は株式会社HAKUへ
HDD・SSDの安全な破棄、データ消去証明書の発行、法人向けの無料回収など、情報機器の処分に関するお悩みはお任せください。累計10,000社を超える取引実績を持つ処分のプロが解決します。