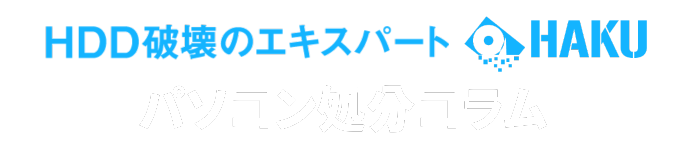企業活動において、パソコンの入れ替えや廃棄は定期的に発生する業務のひとつです。特に数十台、数百台といったまとまった台数を処分する場合、ただ不要になったからといって安易に捨ててしまうわけにはいきません。
法人がパソコンを処分する際に求められるのは、情報漏洩リスクを防ぐ安全性、コストを抑える経済性、そして社内業務の負担を減らす効率性です。これらをすべて満たすためには、信頼できるパートナーを選び、社内での対応も整理しておく必要があります。
この記事では、法人向けパソコン処分における基本的な方法から、業者選びのポイント、安全対策、よくあるトラブルまで、実際の事例を交えてわかりやすく解説します。大量処分でも安心・効率的に進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
法人がパソコンを処分する際に抱える課題

企業におけるパソコン処分は、単なる「ごみの廃棄」ではありません。情報管理、コスト、安全性、社内の運用体制など、いくつもの観点で考慮しなければならない課題があります。ここでは、法人が直面しがちな代表的な3つの課題を解説します。
データ漏洩リスクへの対策が必須
パソコンには、業務データ、顧客情報、社内資料、従業員情報など、機密性の高いデータが数多く保存されています。たとえ電源が入らなくなった古いパソコンでも、ハードディスク(HDDやSSD)にはこれらのデータが残っており、専門的なソフトを使えば復元できてしまうこともあります。
そのため、法人ではデータの完全消去や物理破壊が不可欠です。さらに、実施した証拠として「データ消去証明書」や「破壊証明書」を求められるケースも増えています。万が一、処分したPCから情報が流出すれば、企業の信用や取引先との関係にも大きな影響を及ぼしかねません。
廃棄コストと作業負担のバランス
大量のパソコンを一度に処分する際には、費用と手間のバランスをどう取るかが重要です。たとえば、台数が多い場合、以下のような作業コストが発生します。
- 機器の梱包・運搬
- フロア内の配線取り外しや仕分け
- データ消去作業
- 資産台帳の整理と登録抹消
これらをすべて社内で行うのは大きな負担となるため、業者による一括対応や出張回収サービスの利用が注目されています。また、業者によっては台数や条件に応じて回収費用を無料または低価格で提供しているところもあり、コスト面でも選択肢が広がっています。
法令遵守・社内ルールへの対応
法人としてパソコンを処分する際には、情報セキュリティ方針やコンプライアンスに沿った対応が求められます。また、産業廃棄物としての扱いや、古物商のルールに触れる可能性もあるため、信頼できる業者に任せることがリスク回避に直結します。
加えて、社内でも「IT資産の管理」「証明書の保管」「監査対応」などが必要な場合もあります。特に上場企業や情報管理レベルの高い業界では、処分後の証明管理や社内承認フローの整備が不可欠です。
このように、法人のパソコン処分には「安全性」「効率性」「ルール遵守」の3つを同時に満たす工夫が求められます。次のセクションでは、実際に法人が選べる処分方法について詳しくご紹介します。
法人が取れる主なパソコン処分方法
法人がパソコンを処分する方法はいくつかありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。コスト・安全性・手間・対応スピードなど、自社の状況に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。
メーカーによる回収サービス(PCリサイクルマーク)
国内メーカーの多くは、パソコンに「PCリサイクルマーク」がついていれば、無償で回収してくれる制度を設けています。これは「資源有効利用促進法」に基づいた仕組みで、2003年以降に販売された機種であれば対象となっているケースがほとんどです。
ただし、法人利用の場合は注意が必要です。メーカーによっては、法人向けモデルや大量処分には個別対応が必要となることがあり、一度に多くの台数を処分する場合は、回収申込や手続きに手間がかかることがあります。また、データ消去や証明書の発行に対応していないケースも多いため、セキュリティの観点では不十分となる可能性があります。
自治体による回収制度(※法人は対象外が多い)
一部の自治体では、家庭用の不要なパソコンを小型家電リサイクル法に基づいて回収しています。回収ボックスや持ち込み施設を通じて無料で処分できる制度ですが、法人は原則として対象外です。
また、自治体回収ではデータ消去は行われず、証明書も発行されないため、情報漏洩リスクへの対応としては不十分です。法人の場合は、自治体ではなく専門の回収業者やサービスを利用するのが基本となります。
法人向けパソコン回収業者を利用
近年、多くの企業が利用しているのが、法人向けのパソコン回収業者です。こうした業者は、法人の事情に合わせて柔軟な対応を行っており、以下のようなメリットがあります。
- 大量のパソコン回収に対応(数十〜数百台単位もOK)
- オフィスへの出張回収
- データ消去やHDDの物理破壊、証明書の発行対応
- モニター・周辺機器も同時回収可能
- 条件により無料回収も可能(再販価値や構成による)
社内対応(自社での処理・破壊)
少数のパソコンであれば、自社内でHDDを取り外し、破壊して処分するという方法もあります。物理的に壊すことで情報漏洩リスクは抑えられますが、以下のような課題もあります。
- 社員が作業に慣れていない場合、破損やけがのリスク
- 処分後の筐体・部品を結局業者に依頼する必要がある
- 証明書が発行できないため、監査・内部統制に対応しづらい
このため、HDDを自社で抜き取り、パソコン本体のみを業者に回収してもらうという「ハイブリッド型」もひとつの選択肢です。
このように、法人が取れるパソコン処分方法はさまざまですが、「台数」「社内体制」「必要な証明書の有無」などを踏まえて、最適な方法を選ぶことが大切です。
法人向け回収業者の選び方と比較ポイント
法人が安心してパソコンを処分するには、信頼できる業者選びが何より重要です。ただ「回収してくれる」だけではなく、データの消去体制や料金体系、対応エリア、実績などを総合的にチェックする必要があります。
ここでは、法人がパソコン回収業者を選ぶ際に確認すべき代表的な比較ポイントを紹介します。
データ消去の方法と証明書の有無
まず最も重視すべきは、情報漏洩を防ぐためのデータ消去対応です。業者によって、以下のような違いがあります:
- ソフトウェアによるデータ消去(NIST方式、NSA方式など)
→ 複数回の上書きで復元不能にする方法。法人ではNIST基準準拠が安心材料に。 - HDDの物理破壊
→ 圧壊、穴あけ、破砕などで記録媒体自体を物理的に破壊。 - データ消去証明書・破壊証明書の発行
→ 法人としては、監査対応や社内管理の観点から証明書の発行が必要となるケースが多いです。PDF形式で提供される場合や、現物を郵送してくれる業者もあります。
業者によっては、証明書発行が有料オプションとなっていることもあるため、事前に確認しておきましょう。
対応台数・対応エリア・スピード感
企業によっては、1度に数十台〜数百台を処分することもあります。また、全国に拠点がある場合には、それぞれのオフィスから回収できる業者が必要になります。
- 一度に回収できる最大台数
- 全国対応しているか、地方もカバーしているか
- 申込から回収までのスケジュール感(即日〜1週間以内など)
- 出張回収の可否と、対応可能な地域・条件
スピーディーな対応が求められるケース(移転、リース返却前など)では、回収日を柔軟に調整できる業者が便利です。
料金体系と「無料」の条件
回収費用が無料または格安で済むかどうかは、コスト意識の高い法人にとって重要な判断材料です。ただし、「無料」と表示されていても、条件付きの場合があるため要注意です。
チェックすべきポイントは以下の通り:
- 最低台数や最低金額の条件はあるか?
- HDDが付属していないと無料対象外になる場合は?
- モニターや周辺機器も無料対象か?
- 出張費・梱包材費・証明書発行費などは別途かかるか?
たとえば「送壊ゼロ」は、HDD付きであれば破損品でも送料無料で回収してくれる柔軟な対応が評価されています。
許認可・認証の取得状況
法人として安心して依頼できる業者かどうかを判断するには、以下のような公的な許可や認証の有無も確認しましょう。
- 古物商許可(再販売する業者には必須)
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- プライバシーマーク(Pマーク)
- ISO27001(情報セキュリティ管理)
特に、情報セキュリティや個人情報の管理体制を重視する企業であれば、PマークやISOの取得業者を優先して選ぶのが一般的です。
実績・取引企業・対応事例を確認する
ホームページなどで、これまでの法人対応実績や導入企業名、処分台数などを確認できると、より安心です。特に以下のような実績があれば信頼性が高まります。
- 官公庁、学校法人、大手企業との取引実績
- 同業種・同規模企業での対応事例
- 大量回収・全国一斉回収の実績あり
また、「回収レポート」や「利用者の声」を掲載している業者も信頼性が高い傾向にあります。
このように、法人向けパソコン処分では「安さ」だけでなく、安心・安全・実績を重視した業者選びが重要です。次のセクションでは、社内対応の視点から、社内マニュアルやフロー整備について解説します。
安全性を高めるための社内対応マニュアルの作成ポイント
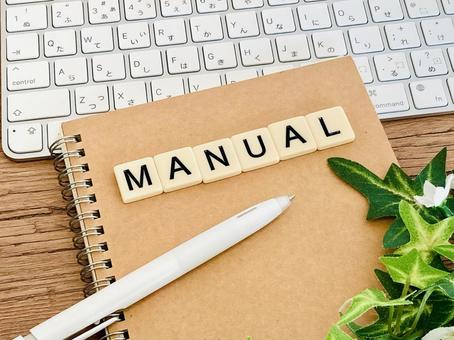
パソコンの処分を安全かつスムーズに進めるには、外部業者への依頼だけでなく、社内の対応体制やルール整備も非常に重要です。特に、情報管理が厳しい企業や上場企業では、内部監査・法令遵守の観点から「社内マニュアル」が必須となることもあります。
ここでは、パソコン処分時の社内対応マニュアルを作成・整備する際のポイントを紹介します。
IT資産廃棄の基本フローを明文化する
まずは、パソコンを廃棄する際の一連の流れを、社内用の業務フローとして明文化しましょう。具体的には以下のようなステップを文書化しておくと有効です。
- 廃棄対象機器のリストアップ(資産台帳との照合)
- 管理部署(総務、情シス)への申請
- データ消去の方法と責任者の決定
- 回収業者の選定・依頼
- 証明書や回収報告書の保管ルール
これらを社内ポータルやマニュアルにまとめておくことで、属人的な処理を防ぎ、ミスや抜け漏れを減らすことができます。
関係部署との連携体制を整える
パソコンの廃棄は1部門だけでは完結しません。以下のように複数部門の連携が不可欠です。
- 情報システム部門:資産管理、データ消去の技術的処理
- 総務部門:契約・業者手配、文書管理
- 経理部門:資産除却、帳簿処理
- 内部統制・監査部門:証憑の確認、運用フローの整合性チェック
マニュアル上で「どの部門が何を担当するか」「どのタイミングで確認・報告を行うか」を明確にしておくことで、トラブルを防ぎ、効率よくかつ監査対応にも強い体制を構築できます。
データ消去・証明書の保管ルール
法人では、パソコン廃棄後に「本当にデータが消去されているか」「正しく破棄されたか」を証明する必要があります。そのため、業者から受け取る以下の書類についても、保管期間や保管方法をルール化しておきましょう。
- データ消去証明書(PDFまたは紙)
- HDD破壊証明書
- 回収完了報告書や納品書
- 資産台帳からの除却記録
これらを社内で数年間保管するよう義務づけることで、万が一のトラブルや社内監査時にもスムーズに対応できます。
定期的な見直しと教育の実施
パソコン処分に関するマニュアルは、数年に一度見直すことが理想です。回収業者の変更、法令の改正、社内の体制変更に応じて内容をアップデートしましょう。
また、異動や新入社員に対しては、社内教育やマニュアルの周知徹底も大切です。特に情シスや総務担当には、データ消去や証明書取得の重要性を共有しておくことで、情報漏洩リスクをさらに低減できます。
処分時に避けたいNG行動とそのリスク

法人としてパソコンを処分する際には、「つい見落としがちな危険」や「軽い気持ちでやってしまいがちなNG行動」がいくつか存在します。これらは、情報漏洩や法令違反、社内トラブルに直結する重大なリスクにつながることも。
ここでは、特に避けるべきNG行動とその背景にあるリスクを解説します。
HDDを入れたまま業者に渡す
一番多いのが、HDD(またはSSD)を入れたままパソコンをそのまま業者に渡してしまうケースです。回収業者によっては、データ消去まで対応していないところもあり、そのまま中古市場に出回ってしまうリスクも。
実際に過去には、法人PCが適切に消去されずに転売され、社内データが流出したというニュースも報じられています。たとえ業者側に悪意がなくても、「自社の責任」として扱われる可能性があるため、HDDの取り扱いには細心の注意を払いましょう。
対策:
- 信頼できる業者を選定する
- 自社でHDDを抜いて保管・破壊する運用を整備する
- データ消去証明書を必ず取得する
許可のない業者に依頼する
「無料で回収します」とうたうチラシや、街中を巡回する回収車などに依頼してしまうと、不法投棄・不適切処理のリスクがあります。
これらの業者は産業廃棄物収集運搬の許可や古物商許可を持っていないことが多く、違法行為に巻き込まれる恐れも。法人がそうした業者に処分を依頼した場合、依頼側にも責任が問われる可能性があります。
対策:
- 業者の許認可(古物商・産廃収集運搬など)を確認する
- 実績や会社情報がしっかり記載されている業者を選ぶ
コストを優先しすぎて重要な対応が抜け落ちる
「とにかく安く済ませたい」という理由で、最安値の業者を選んだ結果、必要な書類や対応がなかったというトラブルもあります。
たとえば、証明書が発行されず、後で監査対応ができなかったり、パソコン本体しか回収してもらえず、周辺機器の処分に別途手間がかかったりするケースがあります。
対策:
- コストとあわせて「対応内容」「サポート範囲」「信頼性」も重視する
- 契約前に対応範囲を細かく確認し、条件を書面で残しておく
回収・廃棄の証明書を保管していない
「処分完了後に証明書が届いたけど、必要ないと思って捨ててしまった」という声も意外と多いです。
しかし、後から社内監査や会計監査で証明の提出が求められる場合があります。
証明書がなければ「本当にデータは消えたのか」「本当に廃棄されたのか」が証明できず、内部統制の面でも問題視されることがあります。
対策:
- 証明書はPDFで社内サーバーに保管、または原本をファイリング
- 保管年数(例:3〜5年)を社内ルールで決めておく
このようなNG行動は、ちょっとした油断や確認不足から起こりやすいものです。しっかりとした体制と業者選定で、リスクを未然に防ぎましょう。
まとめ
法人がパソコンを処分する際には、個人利用と比べてはるかに多くのリスクと責任が伴います。特に情報漏洩は、企業の信用を大きく損なうだけでなく、取引先との関係悪化や法的リスクにもつながりかねません。
そのため、パソコンを単に「捨てる」のではなく、安全に・効率的に・適正コストで処分できる体制を整えておくことが重要です。
本記事でご紹介したように、法人には以下のような選択肢があります。
- メーカーや自治体によるリサイクル制度(台数や対応範囲に制限あり)
- 法人対応に強いパソコン回収業者(全国対応、データ消去証明あり)
- 社内でのHDD抜き取りや処分体制の整備
どの方法を選ぶにしても、業者の信頼性をしっかり確認すること、そして社内での運用ルール(マニュアルやフロー)を明確にしておくことが、トラブルのない処分につながります。
定期的なパソコンの更新や入れ替えは、今後も避けられない業務です。だからこそ、信頼できる処分体制とパートナーを持っておくことで、業務効率と情報セキュリティの両方を守ることができます。
安全でスムーズなパソコン処分を実現するために、ぜひ本記事を社内検討や運用整備の参考にしてみてください。
データ削除・パソコン処分のご相談は株式会社HAKUへ
HDD・SSDの安全な破棄、データ消去証明書の発行、法人向けの無料回収など、情報機器の処分に関するお悩みはお任せください。累計10,000社を超える取引実績を持つ処分のプロが解決します。