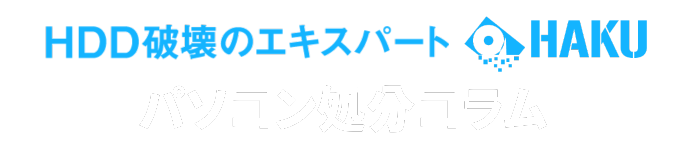パソコンを処分するとき、「とにかく捨てればいい」と思っていませんか?
実はパソコンには、リチウム電池、鉛、水銀、さらにはレアメタルなどの有害・希少な資源が使われており、不適切に廃棄すれば環境汚染や資源の浪費につながります。
また、世界的にも電子機器ごみ(e-waste)の増加が深刻化しており、パソコンの処分方法を見直すことは、地球環境の保護にも直結します。
この記事では、環境負荷をできるだけ低減しながらパソコンを処分する方法を、再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)・法制度・回収業者の選び方などを交えて詳しく解説します。
あなたの一台が「廃棄物」から「資源」に生まれ変わる。そんな地球にやさしい処分方法を、一緒に見ていきましょう。
なぜパソコン処分が環境負荷につながるのか

パソコンの処分が環境に与える影響は、多岐にわたります。以下に、その主な要因を詳しく解説します。
パソコンに含まれる有害物質とその影響
パソコン内部には、以下のような有害物質が含まれています:
- 鉛:はんだ付け部分に使用され、神経系への悪影響が指摘されています。
- 水銀:液晶ディスプレイのバックライトに使用され、環境中に放出されると生態系に深刻な影響を及ぼします。
- カドミウム:バッテリーや半導体に使用され、腎臓障害の原因となる可能性があります。
これらの物質が適切に処理されずに廃棄されると、土壌や地下水の汚染を引き起こし、結果として人間や動植物の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界的に増加する電子廃棄物(e-waste)の問題
近年、電子機器の普及とライフサイクルの短縮により、電子廃棄物(e-waste)の量は急増しています。2019年には、世界全体で約5,360万トンの電子廃棄物が発生し、そのうち正規の処分ルートで回収されたのは17.4%に過ぎません。 このままのペースで増加が続けば、2030年までに7,400万トンに達する見込みです。
特に、先進国から途上国への電子廃棄物の輸出が問題視されています。適切な処理インフラが整っていない地域での不適切な廃棄は、環境汚染や健康被害を引き起こすリスクが高まります。
不適切な廃棄による環境汚染と健康被害
電子廃棄物が不適切に処理されると、以下のような環境汚染が発生します:
- 大気汚染:焼却処理時に有害なガスが発生し、呼吸器系の健康被害をもたらす可能性があります。
- 水質汚染:有害物質が地下水に浸透し、飲料水の汚染を引き起こすリスクがあります。
- 土壌汚染:有害物質が土壌に蓄積され、農作物への影響や生態系の破壊を招く恐れがあります。
これらの汚染は、地域住民の健康被害や生態系の破壊につながる可能性があり、社会全体での対応が求められています。
資源の浪費と持続可能性への影響
パソコンには、金、銀、銅、レアメタルなどの貴重な資源が含まれています。これらを適切にリサイクルしない場合、資源の浪費となり、持続可能な社会の実現に逆行します。例えば、携帯電話1トンには、金鉱石1トンに含まれる金の100倍以上の価値があるとされています。
以上のように、パソコンの不適切な処分は、環境汚染、健康被害、資源の浪費といった多方面での問題を引き起こす可能性があります。そのため、環境負荷を低減する適切な処分方法の選択が重要となります。
環境負荷を低減する主なパソコン処分方法
パソコンを環境に配慮して処分するには、「リユース(再利用)」「リサイクル(再資源化)」「パーツ単位の活用」など、いくつかの選択肢があります。ここでは、それぞれの方法と特徴をわかりやすくご紹介します。
リユース(再利用):再び誰かの手に渡す選択
リユースとは、パソコン本体やパーツを再整備して再利用する方法です。廃棄ではなく、必要な人に使ってもらうことで、環境負荷を大幅に下げることができます。
具体的なリユース方法
- 中古PCとして再販(専門業者やフリマアプリ)
- 学校や福祉施設への寄付・無償提供
- 発展途上国へのリユース支援プログラム
このような方法は、製品寿命を延ばすことにつながり、新たなPCの製造によるCO₂排出や資源使用を抑える効果があります。
リサイクル(再資源化):素材として再利用する
使わなくなったパソコンを分解し、内部の金属やプラスチックなどを素材ごとに分別・再加工して再利用するのがリサイクルです。これは、「PCリサイクルマーク制度」や「小型家電リサイクル法」など、日本国内でも制度化されています。
PCリサイクルマーク制度とは?
- 2003年以降に国内メーカーが販売したパソコンには、回収・再資源化を無料で受けられる「PCリサイクルマーク」が付いています。
- 対象機器にはデスクトップ本体・ノートPC・液晶モニターなどがあります。
- メーカーに申し込むことで専用の回収伝票が送られ、指定の宅配便で無料回収が可能です。
小型家電リサイクル法とは?
- パソコンを含む小型電子機器を、自治体や指定事業者が回収・再資源化する法律。
- 自治体の回収ボックスやイベントでパソコンを処分できることも。
メリット
- 希少金属(レアメタル)など資源の再利用が可能
- ごみの量を減らし、埋立地や焼却処理を不要にできる
- 国や自治体が制度化しているため、安心して利用可能
パーツ単位での再利用:資源活用を最大化
パソコンの一部が故障していても、使える部品だけを取り出して再活用することも立派なエコ活動です。個人でも、以下のような形でパーツ単位のリユースが可能です。
再利用できるパーツの例
- メモリ(RAM)
- ハードディスク(HDD)やSSD
- 電源ユニット
- グラフィックカード(GPU)
- 液晶モニターやキーボード
これらは中古パーツとして販売・交換・譲渡することもでき、電子廃棄物の削減と資源の再利用の両立につながります。
回収業者やメーカーによる再資源化プロセス
近年では、環境配慮型のパソコン回収業者も増えています。これらの業者は、回収したパソコンを丁寧に分解し、以下のようなプロセスで再資源化を行います。
- データ消去(セキュリティ対策)
- 分解・分別(部品ごとに分ける)
- リユース可能品とリサイクル品に分類
- 金属・樹脂など素材ごとに精錬・再利用
一部の業者では、環境マネジメント認証(ISO14001)を取得しているところもあり、より信頼性の高い環境対策を実践しています。
このように、パソコンをそのまま廃棄するのではなく、「活かす」方向に処分方法を選ぶことで、CO₂削減・資源保護・環境汚染防止など、多方面での環境負荷低減に貢献できます。
処分方法別にみる環境負荷比較
パソコンを手放す際の方法によって、環境に与える負荷は大きく異なります。
ここでは代表的な処分方法について、それぞれの環境負荷・CO₂排出・資源循環率などを比較し、どの方法がより環境にやさしいかを解説します。
比較表:主な処分方法と環境負荷の目安
| 処分方法 | 環境負荷 | CO₂排出量 | 資源循環性 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 一般ごみとして廃棄 | 高 | 多い | ほぼゼロ | 不法投棄や埋立てに直結。自治体によっては違法。 |
| 不適正業者へ回収 | 高 | 多い | 不明 | 海外への違法輸出や野積みにより環境被害の恐れあり。 |
| リサイクル業者へ依頼 | 中 | 中程度 | 高 | 素材分別されるが、加工・輸送に一定のCO₂が発生。 |
| リユース(再販売・寄付) | 低 | 少ない | 非常に高い | 製品寿命延長により製造時のCO₂排出を回避可能。 |
| パーツ単位で再利用 | 低 | 少ない | 高 | 破棄を最小限に抑え、製品としての価値を維持。 |
製品寿命を延ばす「リユース」が最も環境にやさしい
もっとも環境負荷が低いのは、**そのまま使える状態で他の人に譲る(リユース)**方法です。製品を新たに製造する際には、原材料の採掘・部品の加工・製造・輸送といった工程で大量のエネルギーが使われ、CO₂排出量は1台あたり約200kg前後とも言われています。
これに対し、リユースによって製品寿命が数年延びれば、その分のエネルギー消費や資源使用を抑えられるのです。
リサイクルは「次善の策」として重要
もし再利用が難しい場合でも、リサイクルに出せば環境への負荷を軽減することが可能です。リサイクルでは、金属・ガラス・プラスチックなどの素材が再資源化されるため、原材料の新規採掘を減らす効果があります。
ただし、分解・精錬・再加工の工程でエネルギーが必要なため、リユースと比べるとやや環境負荷は高くなります。
避けたいのは「不適切な廃棄」
最も避けるべきは、一般ごみとして出してしまう、あるいは不法業者に依頼するケースです。これらの方法では、資源が回収されないだけでなく、有害物質が適切に処理されず、土壌や水質汚染、健康被害のリスクが発生します。
また、法令に違反する可能性もあるため、環境面・法律面の両方で問題がある方法と言えるでしょう。
パソコンの再利用・再資源化が環境に与えるポジティブな影響
パソコンをリユース(再利用)やリサイクル(再資源化)によって処分することは、単に「ごみを減らす」だけでなく、地球環境全体へのポジティブな効果をもたらします。ここでは、そうした具体的な環境貢献の例を紹介します。
CO₂排出量の削減につながる
パソコンの新規製造には、原材料の採掘・加工・組み立て・輸送など、さまざまな工程が必要です。これらすべての過程でエネルギーが使われ、1台あたり平均200〜300kgのCO₂が排出されると言われています。
しかし、再利用やリサイクルによって製品寿命を延ばしたり、資源を再活用したりすれば、新規製造の頻度を減らすことができ、CO₂排出量の削減につながります。
たとえば、中古パソコンを再整備して3年間使用するだけでも、新品を1台製造するのと比べて約80%以上の環境負荷をカットできるという報告もあります。
埋立ごみの削減と焼却処理の抑制
パソコンをそのまま廃棄してしまうと、焼却または埋立処分されることになります。特にプラスチック部品の焼却ではダイオキシンなどの有害ガスが発生することがあり、大気汚染や健康被害につながる恐れがあります。
再資源化によってこうした部品を適切に再利用すれば、廃棄物量を大幅に減らすことができ、焼却炉や埋立地への負担も軽減されます。
レアメタルや貴金属の有効活用(都市鉱山)
パソコンには、金、銀、銅、パラジウムなどの貴重な金属(レアメタル)が多数含まれており、資源としての価値が非常に高いことでも知られています。
実際に、スマートフォンやパソコンなどの電子機器に含まれる金属資源のことを「都市鉱山」と呼び、国内で再資源化する取り組みが進められています。
- ノートパソコン1台から回収できる金:約0.3g(金価格換算で約3,000円前後)
- HDDや基板からも銅やアルミなどが回収可能
これらの資源を再利用すれば、新たな採掘による環境破壊やCO₂排出を防ぐことができ、持続可能な資源利用に大きく貢献します。
循環型社会の実現に貢献
日本では「循環型社会形成推進基本法」に基づき、リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再資源化)の3Rを基本とした社会構築を目指しています。
パソコンの再利用や再資源化は、この「3R」の理念にしっかりと沿った行動です。個人の小さな取り組みであっても、全体で見れば社会全体の環境負荷を確実に減らす大きな力になります。
環境にやさしいパソコン回収業者を選ぶポイント

パソコンを処分する際、「どこに頼むか」は非常に重要です。回収業者によっては、適正な処理を行わず、環境に悪影響を及ぼす可能性もあるため、環境に配慮した業者を選ぶことが大切です。ここでは、信頼できるパソコン回収業者を選ぶためのチェックポイントを紹介します。
再資源化率やリユース率を公開しているか
環境に配慮した業者は、自社で回収したパソコンをどれだけ再資源化・再利用しているかの割合(再資源化率・リユース率)を明示していることが多いです。
この数値が高い業者ほど、「分解・選別・再活用」のプロセスがしっかりしており、環境負荷を抑える処分が期待できます。サイト上や会社案内にその情報が記載されているか、確認してみましょう。
ISO14001など環境関連の認証を取得しているか
ISO14001は、国際的な環境マネジメントシステムの認証で、「企業がどれだけ環境保全に配慮しているか」の指標になります。
このような認証を取得している業者は、廃棄物処理やリサイクルにおいて、環境への影響を最小限にする仕組みを整えている証拠といえます。
加えて、以下のような認可・許可も確認しておくと安心です:
- 古物商許可(中古販売を行う場合)
- 産業廃棄物収集運搬業の許可(法人回収時)
- 個人情報保護方針の明示(データ消去対応)
処分後の流通経路や最終処分方法が明確
優良な回収業者は、回収後のパソコンが「どのように処理され、どこへ流通しているか」を明確にしています。
たとえば:
- 再利用品として整備し、国内の教育機関へ提供
- 素材として精錬され、再生金属として国内メーカーへ納入
- 一部は修理パーツとして回収・再販
こうした透明性のある処理フローを提示している業者は、環境負荷の低減にも本気で取り組んでいると判断できます。
データ消去の信頼性と証明書対応
環境面だけでなく、情報漏洩防止の観点も重要です。パソコンの中には個人情報や業務データが残っているため、データを完全に消去した上で再資源化されることが前提となります。
以下の点を確認しましょう:
- データ消去後に「消去証明書」や「破壊証明書」が発行されるか
- 国際的な消去基準(NIST、DoD)に対応しているか
- 消去・破壊を自社で一貫して行っているか
このような対応があることで、「環境配慮」と「情報管理」の両立が可能になります。
知っておきたい制度・法律
パソコンを適切に処分し、環境への負荷を低減するためには、関連する法律や制度を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、パソコンの処分に関わる主な制度や法令をわかりやすく解説します。
資源有効利用促進法とPCリサイクルマーク制度
「資源有効利用促進法(2001年施行)」は、限りある資源を有効に活用することを目的とした法律で、パソコンメーカーに対して使用済みパソコンの回収とリサイクルの義務を課しています。
その一環として設けられたのが「PCリサイクルマーク制度」です。
PCリサイクルマークとは
- 2003年10月以降に販売された家庭向けパソコンには、このマークが付いています。
- マーク付き製品は、メーカーが無償で回収・再資源化を行います。
- 回収対象は、ノートPC、デスクトップPC、液晶モニターなど。
この制度を利用すれば、廃棄時の費用負担を抑えつつ、環境に配慮した処分が可能です。
小型家電リサイクル法
「小型家電リサイクル法(2013年施行)」は、パソコンを含む家電製品を再資源化するための法律です。自治体や認定事業者が小型家電を回収し、金属資源のリサイクルを促進することを目的としています。
主な特徴
- 対象:パソコン・携帯電話・デジカメ・プリンターなど約400品目
- 回収方法:自治体の回収ボックス、イベント回収、宅配回収など
- 費用:原則無料(自治体によって異なる)
この制度を活用することで、手軽かつ合法的にエコな処分が実現できます。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い(法人向け)
法人でパソコンを処分する場合は、「廃棄物処理法」の適用も意識する必要があります。
- 個人利用のPC → 一般廃棄物
- 法人所有のPC → 産業廃棄物(情報機器類)
産業廃棄物を処分するには、許可を持った収集運搬業者・処分業者に依頼しなければなりません。違反すると罰則を受ける可能性もあるため、特に法人は注意が必要です。
環境省・経済産業省によるリサイクル推進策
国もパソコンを含む電子機器のリユース・リサイクルを促進するため、以下のような取り組みを行っています:
- 環境省による「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」
- 経済産業省が支援する「3R推進協議会」
- デジタル庁・文部科学省によるPC再利用推進(教育用途)
こうした政府の後押しを活用すれば、コストを抑えながら持続可能な処分が可能になります。
このように、法令や制度を知っておくことで、「環境にやさしいだけでなく、法的にも適正なパソコン処分」が実現できます。
個人でできるパソコン処分時のエコアクション
環境にやさしいパソコン処分は、企業や自治体だけの取り組みではありません。私たち一人ひとりが意識を変えることで、大きな環境改善につながります。
ここでは、個人でも今日から実践できるエコなパソコン処分のアクションをご紹介します。
再利用できる状態での譲渡・寄付を検討する
まずは「使えるかどうか」を見直してみましょう。多少古くても、OSが動作し、基本的な操作が可能なパソコンであれば、まだ十分に再利用できる可能性があります。
譲渡・寄付先の例
- 地域の学校や教育NPO
- 高齢者施設や福祉団体
- 無償引取を行うパソコン再生業者
- ジモティーや地域の掲示板(直接取引)
一人で不要になったパソコンが、誰かの役に立つ「資源」として生き返ることもあるのです。
不要パーツをオークションやフリマアプリで活用
完全に壊れてしまったパソコンでも、内部パーツや周辺機器は再利用可能な場合があります。以下のようなパーツは中古市場でもニーズがあります:
- メモリ・SSD・HDD
- グラフィックボード・電源ユニット
- 液晶モニターやキーボード・マウス
ヤフオク、メルカリなどで「部品取り用」として出品すれば、他のユーザーの修理用部品として活用されることも多いです。
メーカーや回収業者のエコ回収を活用する
不要になったパソコンは、メーカーや認定業者が提供する無料回収プログラムを利用することで、適正かつ環境に配慮した方法で処分できます。
例:
- メーカーの「PCリサイクルマーク」を活用(無料で回収)
- 一部業者では「パソコン1台送ると、1本の植林」などのCSR活動と連動した回収サービスも
公式なルートで処分すれば、データ消去も含めて安心して手放すことができるのもポイントです。
分解・分別処理は無理せずプロに依頼を
「どうせ壊れているから自分で分解して捨てよう」と思う方もいますが、パソコンの分解にはリチウム電池や高電圧部品など危険も伴います。
環境のために自力で分別しようとして事故につながるケースもあるため、回収のプロに任せる方が安全で確実です。
「まとめて捨てる」ではなく「選んで活かす」意識を
大量にたまった古いパソコンや周辺機器を一気に処分しがちですが、中にはまだ価値ある資源が含まれている可能性も。
「これは再利用できるか?」「どこに出せば資源になるか?」とひとつひとつ丁寧に判断することが、環境への思いやりにつながります。
まとめ
パソコンを処分するという行為は、単なる「ゴミ出し」ではなく、地球環境に対して大きな影響を与える選択でもあります。適切な方法で処分を行うことで、CO₂排出の削減、有害物質の流出防止、貴重な資源の再利用といった持続可能な社会の実現に貢献することができます。
本記事でご紹介したように、リユース(再利用)やリサイクル(再資源化)は、環境負荷を低減するうえで非常に効果的です。また、パソコン回収に関する法律や制度を正しく理解し、信頼できる回収業者やメーカーの制度を活用することが、より安全かつ環境にやさしい処分への第一歩となります。
個人の行動が環境に与える影響は小さいようでいて、積み重なれば大きな力になります。
パソコンを「捨てる」のではなく「活かす」意識を持ち、次の世代によりよい地球環境を残すための選択をしていきましょう。
株式会社HAKUは「人と企業から喜ばれる企業」を理念とし、地球にやさしいパソコン回収、処分を行なっております。パソコン処分の際は是非お気軽にお問い合わせください。